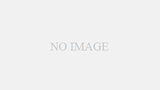新年会の司会を任されたけれど、何から準備すれば良いか不安…そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では、初めてでも安心して進められるように、新年会の司会進行の流れや挨拶の順序をわかりやすく整理しました。
さらに、シーンごとに使える挨拶例文や、実際にそのまま読み上げられるフルバージョンの進行台本も収録しています。
読み終えれば、「開会から閉会までどのように進めればよいか」が一目でわかり、当日の緊張もぐっと和らぎます。
新年会を成功に導く司会進行の完全ガイドとして、ぜひ活用してください。
新年会司会の基本ガイド
ここでは、新年会の司会者として最低限押さえておきたい基本を解説します。
役割や必要な準備を理解することで、自信を持って本番に臨めるようになります。
司会者の役割と必要なスキル
新年会の司会者は、単に進行を読み上げる人ではありません。
会全体の流れを整え、参加者が安心して楽しめる空気を作る大切な役目があります。
「進行をコントロールする案内役」と「場の雰囲気を支えるサポーター」の2つの顔を持つのが司会者です。
必要とされるスキルは、難しいものではありません。
| スキル | 具体例 |
|---|---|
| 聞き取りやすい声 | 一文を短く区切り、はっきり発音する |
| 場の観察力 | 静かになったら軽く声をかける |
| 柔軟な対応力 | 予定が前後したら自然に言葉を添える |
これらを意識すれば、特別な経験がなくても十分務まります。
大切なのは「完璧に進める」ことよりも「全体を心地よくまとめる」意識です。
事前準備と進行台本の作り方
本番を安心して迎えるために、事前準備は欠かせません。
特に、進行台本(シナリオ)があるかどうかで、司会の安心感が大きく変わります。
進行台本には、以下の内容を盛り込むと便利です。
- 開会から閉会までの大まかな流れ
- 挨拶を依頼する人の名前と役職
- 余興や催し物の順番と担当
- 各場面での案内フレーズ
例えば、台本の一部はこんな形になります。
| シーン | 司会のセリフ例 |
|---|---|
| 開会 | 「皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。ただいまより新年会を始めます。」 |
| 乾杯案内 | 「それでは、〇〇部長にご発声をお願いしたいと思います。皆様ご準備ください。」 |
| 閉会 | 「以上をもちまして本日の新年会を終了いたします。お気をつけてお帰りください。」 |
「台本がある=安心材料」と考えると良いでしょう。
丸暗記する必要はなく、手元にメモとして置いておくだけでも心強い味方になります。
新年会の進行全体の流れ
この章では、新年会の全体像を整理してお伝えします。
一連の流れを把握しておくことで、当日の進行をイメージしやすくなり、落ち着いて司会ができます。
開会から閉会までの基本ステップ
新年会の進行は、どの会社や団体でも大きくは変わりません。
以下の流れを押さえておけば、自然に会をまとめられます。
| 順番 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 開会の言葉 | 司会または幹事が「始まりの合図」をする |
| 2 | 主催者や上役の挨拶 | 感謝や新年の抱負を語る場面 |
| 3 | 乾杯 | 参加者全員が気持ちを合わせる大切な瞬間 |
| 4 | 食事・歓談 | 自由に交流する時間。適度なアナウンスが効果的 |
| 5 | 余興・ゲーム・表彰 | 場を盛り上げる要素。タイミングを意識する |
| 6 | 中締め | 一度区切りを入れることで会が整う |
| 7 | 閉会の言葉 | 司会や幹事が最後のまとめを伝える |
この流れを覚えておけば「いつ、誰にバトンを渡すか」が自然に見えてきます。
規模や形式に応じた進行の違い
基本の流れは同じでも、規模や形式によって少しアレンジが必要です。
| シーン | 小規模(10〜20人) | 大規模(50人以上) |
|---|---|---|
| 開会 | カジュアルな挨拶でスタート | きちんとした開会宣言を用意 |
| 乾杯 | 参加者全員で声を合わせる雰囲気 | 役職者をしっかり紹介して進行 |
| 余興 | 簡単なゲームや自己紹介タイム | 企画担当が準備した演出や表彰 |
| 閉会 | 司会者が簡潔にまとめる | 役職者の挨拶を経て正式に終了 |
たとえば、部署内だけの小さな集まりならカジュアルに進めても問題ありません。
一方で、全社や取引先が参加するような場では、フォーマルさを意識した進行が求められます。
「会の性質に合わせて進行を調整する」ことが司会者の腕の見せどころです。
挨拶の順序と人選のルール
新年会の司会で特に重要なのが「挨拶の順番」と「誰にお願いするか」です。
この2つを間違えると場がぎこちなくなるため、あらかじめしっかり準備しておきましょう。
開会・乾杯・中締め・閉会の基本順序
挨拶には定番の順序があります。
これを押さえるだけで全体の進行がスムーズになります。
| 場面 | 担当する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 開会の挨拶 | 最も役職の高い人 | 新年の抱負や感謝を込めた話をする |
| 乾杯の音頭 | 役職で三番目の人 | テンポよく全員の気持ちを盛り上げる |
| 中締め | 役職で二番目の人 | 会を一度整えて次の展開につなげる |
| 閉会の言葉 | 司会者または幹事 | 簡潔に感謝を伝えて終了する |
「開会は一番上、乾杯は三番目、中締めは二番目、閉会は司会者」と覚えておくと混乱しません。
誰にどの挨拶を依頼するべきか
挨拶を依頼するときは、役職の序列だけでなく「その人らしさ」も考慮するとよいです。
- 明るく場を盛り上げられる人 → 乾杯の音頭に向いている
- 落ち着いてまとめられる人 → 中締めに最適
- きちんと伝えるのが得意な人 → 開会や閉会の挨拶に適任
また、依頼はできるだけ早めに行いましょう。
直前の依頼は相手に負担になるため、数日前にお願いしておくのがマナーです。
想定外の欠席や急な変更時の対応法
新年会当日、急な欠席や予定変更が起こることもあります。
そんなときに備えて「代役候補」を考えておくと安心です。
| 場面 | 代役の例 |
|---|---|
| 開会の挨拶 | 次に役職が高い人 |
| 乾杯 | 同部署の次席クラス |
| 中締め | 進行をよく理解している幹部 |
| 閉会 | 司会者自身で対応可能 |
「必ず誰かに代わりを頼める」体制を作っておくことが、司会の安心材料です。
進行をスムーズにする司会のコツ
新年会を任された司会者にとって、最も大切なのは「会場全体を心地よくまとめること」です。
ここでは、進行を滞りなく進めるための具体的なコツを紹介します。
場の雰囲気を和ませる工夫
司会者の声のトーンや言葉遣いは、会場全体の空気を左右します。
例えば、開会のときに少し柔らかい言葉を添えるだけで、緊張感が和らぎます。
| 場面 | 一言例 |
|---|---|
| 開会 | 「今日は皆さんでゆったり過ごしていただければと思います」 |
| 歓談中 | 「お料理やお話を楽しみながら、思い思いにお過ごしください」 |
| 余興前 | 「ここからは少し趣向を変えて、盛り上がる時間にしていきましょう」 |
短い言葉で安心感を与えるのが、場を和ませる秘訣です。
時間管理と臨機応変な対応力
新年会では、予定より進行が早まったり遅れたりすることがあります。
そんなときは「時計を見ながら余興を短めにする」「歓談を少し延ばす」など、柔軟に調整しましょう。
- 余興が長引いた場合 → 次のアナウンスを簡潔にする
- 時間が余った場合 → 雑談や一言コメントでつなぐ
- 予定外の場面 → 「ここで急きょ〇〇さんにご登場いただきます」と自然に紹介
進行が多少前後しても「自信を持って進めること」が大切です。
マイクの使い方と声の出し方
どんなに良い進行も、声が届かなければ意味がありません。
マイクは口元からこぶし1つ分離し、一定の距離を保ちましょう。
| 注意点 | 理由 |
|---|---|
| 口に近すぎない | こもった音になり聞き取りづらい |
| 一定の音量を保つ | 声が小さすぎると後方に届かない |
| 間を意識する | ゆっくり話すと聞き手が理解しやすい |
声の大きさは「後ろの人に届くかな?」と意識するだけで自然と安定します。
聞き取りやすさは司会者にとって最大の武器です。
新年会で使える挨拶例文集(シーン別)
ここでは、実際にそのまま使える挨拶例文を紹介します。
シーンに合わせて使い分けられるように、複数のパターンを用意しました。
開会の挨拶(短め・丁寧・カジュアルの3パターン)
まずは開会の場面で使える例文です。
| パターン | 例文 |
|---|---|
| 短め | 「皆さま、本日はお集まりいただきありがとうございます。ただいまより新年会を始めます。」 |
| 丁寧 | 「新年あけましておめでとうございます。本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。心ゆくまで楽しい時間をお過ごしください。」 |
| カジュアル | 「皆さん、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。それでは乾杯までのひとときを、どうぞお楽しみください。」 |
乾杯の音頭紹介(立場別のアナウンス例)
乾杯に入る前に、司会が一言添える場面です。
- 上役にお願いする場合
「それでは、ここで〇〇社長に乾杯のご発声をお願いしたいと思います。」 - 中堅クラスにお願いする場合
「続きまして、〇〇部長に乾杯の音頭を取っていただきます。」 - フランクに進めたい場合
「皆さんグラスの準備はよろしいでしょうか。それでは〇〇課長、お願いします。」
乾杯前はテンポよく進めると、会全体が盛り上がります。
余興やゲーム・表彰の案内例
余興やゲームを進行する際の例文です。
| シーン | 例文 |
|---|---|
| 余興開始 | 「ここで皆さんお待ちかねの余興タイムです。まずは〇〇チームの出し物からどうぞ。」 |
| ゲーム案内 | 「続きましてゲームコーナーを始めます。景品もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。」 |
| 表彰 | 「ここで今年特に活躍された方々の表彰を行います。受賞者の皆さまは前へお進みください。」 |
中締め・閉会の挨拶例(複数バリエーション)
会の終盤に必要な挨拶です。雰囲気に合わせて使い分けましょう。
- 中締め例
「本日の会も盛り上がってまいりましたが、ここで一度中締めとさせていただきます。〇〇専務、お願いいたします。」 - 閉会(丁寧)
「本日は最後までご参加いただき、誠にありがとうございました。これにて本日の新年会を終了いたします。」 - 閉会(カジュアル)
「そろそろお時間となりました。本日の新年会はこれでお開きです。皆さま、どうぞ気をつけてお帰りください。」
閉会の挨拶は長くせず、簡潔にまとめることが好印象です。
フルバージョン司会進行台本(完全サンプル)
ここでは、新年会を最初から最後まで通して進行できる「完全版の司会台本」を紹介します。
実際にこのまま読み上げても使えるように構成しています。
冒頭〜開会の流れ(司会の第一声〜開会挨拶)
「皆さま、本日はお集まりいただきありがとうございます。
ただいまより、株式会社〇〇の新年会を始めさせていただきます。
本日の司会を務めます△△です。どうぞよろしくお願いいたします。」
「それでは、開会にあたりまして、代表取締役の〇〇社長よりご挨拶をいただきます。〇〇社長、お願いいたします。」
乾杯までの流れ(紹介・乾杯)
「〇〇社長、ありがとうございました。
続きまして、新しい年の始まりを祝して乾杯を行いたいと思います。
乾杯のご発声は、〇〇部長にお願いしております。
皆さま、グラスのご準備をお願いいたします。」
(乾杯後)
「〇〇部長、ありがとうございました。
それではどうぞ、お食事とお話を楽しみながら、ゆったりとお過ごしください。」
歓談・余興パートの案内例
(歓談中の一言)
「皆さま、会場内のお料理やお飲み物はどうぞご自由にお楽しみください。」
(余興スタート時)
「ここで少し趣向を変えて、余興のお時間に移りたいと思います。
トップバッターは〇〇チームの皆さんです。会場の皆さま、大きな拍手をお願いします。」
中締めから閉会までのまとめ進行
「楽しい時間もそろそろ佳境に入ってまいりました。
ここで中締めとして、〇〇専務にご挨拶をいただきます。〇〇専務、お願いいたします。」
(中締め後)
「〇〇専務、ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の新年会は終了となります。
皆さま、最後までご参加いただき、誠にありがとうございました。
どうぞお気をつけてお帰りください。」
| シーン | 司会のセリフ例 |
|---|---|
| 冒頭 | 「皆さま、本日はお集まりいただきありがとうございます。本日の司会を務めます△△です。」 |
| 開会 | 「これより新年会を始めます。まずは〇〇社長よりご挨拶をいただきます。」 |
| 乾杯 | 「乾杯のご発声は〇〇部長にお願いいたします。皆さまご準備ください。」 |
| 歓談 | 「お料理と会話をどうぞごゆっくりお楽しみください。」 |
| 余興 | 「続いて余興のお時間です。最初は〇〇チームの皆さんにご登場いただきます。」 |
| 中締め | 「ここで中締めとして〇〇専務よりご挨拶をいただきます。」 |
| 閉会 | 「本日はありがとうございました。これにて新年会を終了いたします。」 |
この流れをひと通り押さえておけば、どんな新年会でも安心して司会ができます。
司会を成功させる実践テクニック
新年会をスムーズに進めるためには、進行の台本だけでなく、ちょっとした工夫や心がけが大切です。
ここでは、実際に役立つテクニックをまとめました。
時間管理とアドリブ対応
時間配分を守ることは、参加者にとって安心感につながります。
予定より遅れている場合は余興や歓談を短めに調整し、早まっている場合は一言コメントを加えて間を埋めましょう。
| 状況 | 対応例 |
|---|---|
| 時間が押している | 「続きましてのプログラムに移らせていただきます」 |
| 時間が余った | 「ここで少しだけ皆さまにお話を伺いたいと思います」 |
| 急な変更 | 「予定を一部変更して、この後は〇〇さんにお願いすることになりました」 |
「臨機応変な一言」が言えると、会全体が自然にまとまります。
場を和ませる声かけの工夫
場が少し静かになったときに、司会から軽い一言を添えると空気が和みます。
- 「皆さま、楽しんでいただけていますでしょうか」
- 「お隣の方ともぜひお話を広げてみてください」
- 「ここからは少しリラックスして進めてまいります」
ちょっとした声かけが、参加者同士の距離を縮めるきっかけになります。
失敗を防ぐチェックリスト
司会者としてよくある失敗は、事前準備で防げます。
当日を迎える前に、以下のチェックリストを確認しておきましょう。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 挨拶者リスト | 役職・名前・読み方を確認したか |
| 進行表 | 台本に沿って全体の流れを把握したか |
| マイク | 音量や使い方をリハーサルしたか |
| 余興やゲーム | 担当者や順番を確認したか |
「事前準備+当日の柔軟さ」で、司会は安心して進められます。
まとめ:自信を持って新年会の司会を務めるために
新年会の司会は、最初から最後まで会を導く重要な役割です。
ここまで紹介してきた流れや例文を押さえておけば、初めてでも安心して進行できます。
この記事から学べるポイント総整理
本記事で解説した内容を振り返りましょう。
- 司会者の役割は「進行役」と「雰囲気づくり」
- 開会から閉会までの流れは「開会 → 挨拶 → 乾杯 → 歓談 → 余興 → 中締め → 閉会」
- 挨拶の順序は「開会=最上位、乾杯=三番目、中締め=二番目、閉会=司会者」
- 例文を複数用意しておくと当日安心
- 時間管理と臨機応変な対応で全体がまとまる
要は「台本+心配り」で、誰でも安心して司会を務められるということです。
司会者として成長するヒント
新年会の司会は、一度経験すると次回からグッと気持ちが楽になります。
毎回の経験が、自分の進行スキルを高めるチャンスです。
- うまくいった点を次回も活かす
- 言葉に詰まった場面をメモしておき、改善する
- 他の司会者の進め方を観察して参考にする
小さな工夫の積み重ねで、自然と「安心感のある司会者」になっていきます。
大切なのは完璧さよりも、参加者が気持ちよく過ごせる空気を作ることです。
この記事を参考に、自信を持って新年会の司会進行に臨んでください。